チームの成功には、心理的安全性が欠かせません。
しかし、心理的安全性の実現にはぬるま湯の罠に陥ることがあります。
この記事では、心理的安全性とぬるま湯の違いを探ります。
そして、ぬるま湯とは異なる、具体的な心理的安全性の作り方についても解説します。

この記事を読んで分かること。
- 心理的安全性とは
- チームの成功における心理的安全性の役割
- ぬるま湯とは
- 心理的安全性とぬるま湯の違い
- ぬるま湯とは違う心理的安全性の作り方
心理的安全性とは
安心感と開放感を提供
心理的安全性は、メンバーが自由に意見や考えを出し合える安心感と開放感を提供する環境を指します。
この環境が整っていると、メンバーは恐れることなくアイデアを提案し合い、コミュニケーションが円滑になります。

リスクを恐れずに挑戦
心理的安全性がある環境では、メンバーは失敗やリスクを恐れることなく新しいアイデアや解決策に挑戦できます。
これにより、チームの成長とイノベーションが促進されます。

信頼と共感の構築
心理的安全性がある環境では、メンバー同士が互いを尊重し、信頼関係を築きながら共感し合うことができます。
これにより、チームの結束力が高まります。

チームの成功における心理的安全性の役割
イノベーションと成長の促進
心理的安全性がある環境では、メンバーが新しいアイデアを提案しやすくなり、イノベーションと成長が促進されます。
これにより、チームは競争力を高めることができます。

エンゲージメントとモチベーションの向上
安心して意見を述べられる環境があると、メンバーのエンゲージメントとモチベーションが向上します。
これにより、チームの生産性が向上します。

問題解決とコンフリクトの円滑化
心理的安全性がある環境では、メンバーが問題やコンフリクトをオープンに議論し、円滑に解決できる環境が整います。
これにより、チームの効率性が向上します。

ぬるま湯とは
挑戦や成長の停滞
ぬるま湯の状態では、チームの挑戦や成長が停滞し、新しいアイデアや解決策が生まれにくくなります。
これにより、チームの競争力が低下します。

モチベーションの低下
ぬるま湯の環境では、メンバーのモチベーションが低下し、チームのパフォーマンスが低下します。
これにより、目標達成が困難になります。

競争力の低下
ぬるま湯の状態では、チームの競争力が低下し、市場の変化に適応できなくなる可能性があります。
これにより、チームの存続が危ぶまれます。

心理的安全性とぬるま湯の違い
挑戦と成長の姿勢
①心理的安全性
心理的安全性がある環境では、メンバーは挑戦を恐れずに新しいアイデアを提案し、成長を促進します。
失敗を恐れずにリスクを取り、学びの機会として捉えます。

サントリーの「やってみなはれ」の精神を思い出します。
「やってみなはれ」の精神
サントリー創業の志「やってみなはれ」。
これは、創業者・鳥井信治郎の口癖でした。
やってみよう。
やってみなければわからない。
「新しい価値創造」を企業理念とするサントリーを表すこの言葉は、創業当初から今でも全社員の心のなかに生き続けています。
企業理念 サントリー採用情報 (suntory.co.jp)

②ぬるま湯
一方、ぬるま湯の状態では、挑戦やリスクを避け、現状維持を好む傾向があります。
新しいアイデアやアプローチに取り組む意欲が低下し、成長の機会が制限されます。
コミュニケーションとフィードバック
①心理的安全性
心理的安全性の高い環境では、メンバー同士がオープンかつ建設的なコミュニケーションを行い、フィードバックを受け入れる文化が根付きます。
メンバーは自身の意見や感情を率直に表現し、他者の意見を尊重します。
②ぬるま湯
ぬるま湯の状態では、コミュニケーションが十分に行われず、フィードバックの受け入れが難しい状況が生まれます。
メンバーは自身の意見を抑え、問題や懸念を声に出すことを避ける傾向があります。

チームの目標への取り組み
①心理的安全性
心理的安全性が高いチームでは、メンバーはチームの目標に対して共感し、積極的に取り組みます。
チーム全体が協力し合い、目標達成に向けて努力します。
②ぬるま湯
ぬるま湯の状態では、メンバーの目標への取り組みが低下し、個々の関心や利益が優先される傾向があります。
チーム全体の協力や連携が欠如し、目標達成が困難になります。

これらの違いを考慮することで、心理的安全性を高めつつ、ぬるま湯の状態を回避し、チームの成長と成功に貢献する方法を見出すことができます。
ぬるま湯とは違う心理的安全性の作り方
コミュニケーションの促進
心理的安全性を高めるためには、積極的なコミュニケーションを促進することが重要です。
具体的には以下の点に注意します。

①オープンな雰囲気の醸成
チームメンバーが自由に意見交換できる雰囲気を作り出します。
定期的なミーティングやフィードバックセッションを通じて、メンバーが率直に意見を述べることができる環境を整えます。
②聴く姿勢の養成
メンバー同士がお互いを尊重し、相手の意見や感情を真剣に受け止める姿勢を養います。
アクティブリスニングの技術を身につけることで、コミュニケーションの質が向上します。
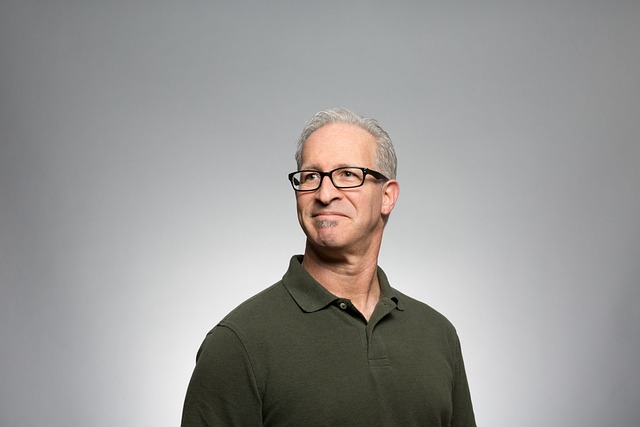
③適切なコミュニケーションツールの活用
チーム内のコミュニケーションを効率化するために、適切なコミュニケーションツールやプラットフォームを活用します。
チャットツールやプロジェクト管理ツールを適切に活用することで、情報共有と円滑なコミュニケーションを促進します。
フィードバック文化の育成
心理的安全性を高めるためには、フィードバック文化を育成することが重要です。
具体的には以下の点に注意します。

①定期的なフィードバックセッションの実施
チームメンバー同士が定期的にフィードバックを交換する機会を設けます。
フィードバックは適切な形で伝えられ、受け手が成長や改善に役立つように心がけます。
②建設的なフィードバックの提供
フィードバックは建設的で具体的なものであることが重要です。
過去の成果や行動を踏まえて、改善点や肯定的な側面を含めたフィードバックを提供します。

③フィードバックへの感謝と受容
フィードバックを受け取った際には、感謝の意を示し、受け入れる姿勢を示します。
フィードバックを受け取ることで自己成長を促進し、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献します。
相互理解とサポート
心理的安全性を高めるためには、メンバー同士の相互理解とサポートが不可欠です。
具体的には以下の点に注意します。

①エンパシーの育成
チームメンバーはお互いの立場や視点を理解し、共感することが重要です。
エンパシーを育てるために、相手の立場に立って物事を考える習慣を身につけます。
②問題解決への協力
チームメンバーは困難な状況に直面した際には、お互いを支え合いながら問題解決に取り組みます。
チーム全体で協力し、効果的な解決策を見出すために努力します。

③感謝と励ましの文化の醸成
チーム内での成果や努力に対する感謝と励ましの文化を醸成します。
メンバーがお互いをサポートし、成果を称え合うことで、チームの結束力が高まります。
これらのアプローチを実践することで、心理的安全性を高め、チームのパフォーマンスと成果を向上させることができます。

心理的安全性を理解するおすすめ本:3選
心理的安全性の作り方:著者 石井遼介
- 日本の人事部「HRアワード2021」書籍部門 優秀賞受賞!
- 「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」マネジメント部門賞受賞!
- 『週刊東洋経済』ベストブック2021特集「ビジネス書」ランキング 第2位
最高のチームはみんな使っている 心理的安全性をつくる言葉55:著者 石井遼介
いつものひと言を変えることで……
会話が増える!
チャレンジが始まる!
チームが変わる!
心理的安全性 最強の教科書:著者 ピョートル・ヘリクス・グジバチ
著者は、Google元アジア・パシフィック人財・組織開発責任者。
20年間、日本で働いた経験を元に、日本のビジネスパーソンのために書き下ろした一冊。
「チームが最高の成果を生む鉄則」
まとめ
この記事では、心理的安全性とぬるま湯の違いを3つの観点から比較し、ぬるま湯とは異なる心理的安全性を構築する方法を提案しました。
具体的には以下のポイントが挙げられます。

心理的安全性とは
安心感と開放感の提供、挑戦への促進、信頼と共感の構築が重要です。
チームの成功における役割
イノベーションと成長の促進、エンゲージメントとモチベーションの向上、問題解決とコンフリクトの円滑化が期待されます。
ぬるま湯とは
挑戦や成長の停滞、モチベーションの低下、競争力の低下が特徴です。

心理的安全性とぬるま湯の違い
挑戦と成長の姿勢、コミュニケーションとフィードバック、チームの目標への取り組みが異なります。
ぬるま湯とは違う心理的安全性の構築方法
ミュニケーションの促進、フィードバック文化の育成、相互理解とサポートが重要です。
これらの要点を考慮することで、心理的安全性を高め、チームのパフォーマンスと成果を向上させることができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
いかがでしたか?
職場にはいろんなトラブルメーカーがいます。
それは上司であったり、同僚であったり、部下であったり・・・

大切なことは、あなたの立場に関わらず、あなたが主体的な意思を持つこと。
「自分はどうしたいのか?」
自分の意思を持つことは、心理的安全性とぬるま湯の違いを知ること以上に大切なことだと思います。
この記事に興味を持ってくれた方には、以下の記事もおすすめです。
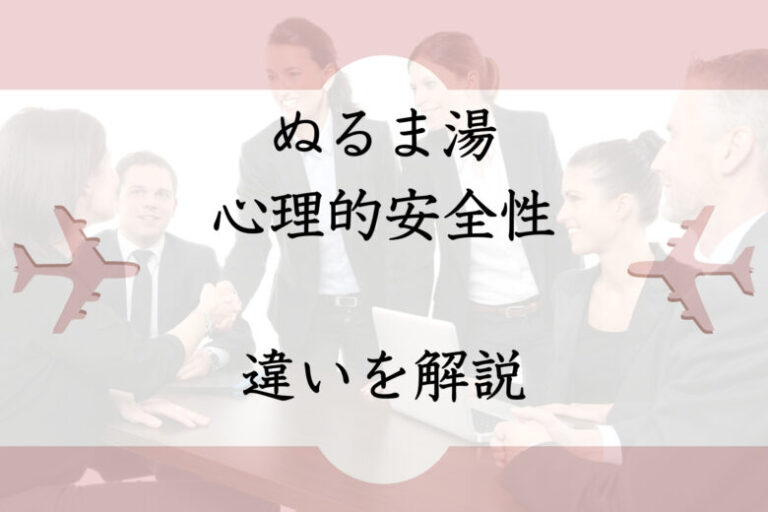
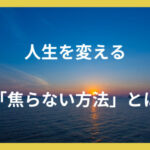

コメント