みなさん、こんにちは。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
感謝いたします。
私は現在、とある東証プライム上場企業にて現役の管理職(正の課長)をしています。
一方で、私の職位は部長クラスです。
どういうことかと申しますと、部長や副部長ではないけれど、課長でなくなったら、〇〇部長という役職名になる、と思っていただければ結構です。
もちろん、部長や副部長を目指していますよ。
この記事では、「私がいかにして部長クラスまで到達したのか」を紹介したいと思います。
この記事は、以下の方々を対象に記載しています。
昇進・昇格 マネジメントとは何なのか?

そろそろ、私の先輩が昇進・昇格試験を受ける時期ですが・・・
管理職への昇進・昇格試験って、何が問われるのでしょうか?

企業によって昇進・昇格試験の内容は様々だと思いますがが、
私が管理職になるときに、どんなステップを踏んだのか、
そしてどんな試験があったのかをご紹介したいと思います。

ありがとうございます。生々しい話が聞けそうですね。

その前に簡単ですが、マネジメントとは何か?について紹介したいと思います。
マネジメントとは、直訳すると「経営」となります。
つまり、管理職とは「組織の経営者」と考えていただければと思います。

「組織の経営者」ですか・・・
あまり意識したことはなかったです。


正直、私も昇進・昇格試験を受けるまではあまり意識していませんでした。
私が意識していたのは、
「管理職になって給料を上げたい」というものでした(笑)
ただ、通常の業務においても「意思決定」することは多かったので、
メンバーの意思決定をサポートしていけばいいのかな?
くらいに考えていました。

ということは、それだけではないのですか?

はい。
管理職にとっては、業務の意思決定よりも、
もっと大事なことがあります。
順を追って紹介させていただきます。
①管理職としての方針を策定する

これが管理職に与えられたもっとも大きな権限といえます。
しかし、あまり難しく考える必要はありません。

そうなんですか?
これが一番、難しいように思うのですが?

すみません、言い方が悪かったですね。
なぜ、難しく考えなくてよいかというと、
組織の方針というのは、
基本的に上位組織の方針に沿ったものとなるからです。

上位組織の方針に沿ったもの?

一般的な組織の階層は、事業部→部→課→グループなどですが、
- 事業部であれば、会社の方針に従う
- 部であれば、事業部の方針に従う
- 課であれば、部の方針に従う
- グループであれば、課の方針に従う
ということです。

なるほど!分かりました。
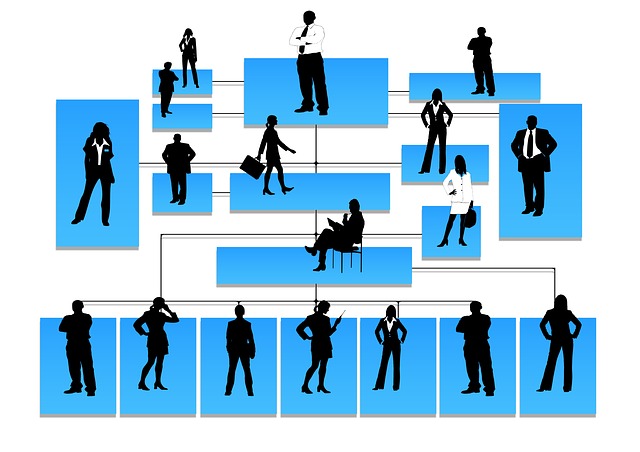

その上位方針に従って、自分の組織は何をするのか?
具体的には、
自分の預かった組織をさらに細分化するかしないか、
自分のサブリーダーを設置するかしないか、
経験の浅いメンバーに育成担当をつけるかつけないか、などです。
また、部下の誰に・どんな役割と責任を担ってもらうのかといった、
役割分担を決めることも管理職としての方針の一つです。

なるほど・・・
上司から「〇〇君のフォローをしてくれ」などと言われることもありますが、
このような全体像の一つだったのですね。

担当者のうちは、目の前の業務で精一杯のこともあるかもしれません。
私もある時期から、課長に「これについてどう思う?」などと頻繁に相談を受けるようになり、管理職業務の全体像を意識するようになった感じです。
②方針を遂行するためにリーダーシップを発揮する

ここでいうリーダーシップとは、
自身が策定した方針を遂行するために部下を指揮することだけではありません。

え!? 他に何があるのですか?

自分の上司や関係部署の責任者に動いてもらうためにも、
リーダーシップを発揮しなければなりません。

よくいう「根回し」みたいなものでしょうか?


何かを円滑に進めるうえで、必要であれば「根回し」も行います。
この根回しを行ううえでも、
より円滑に進めるためにはどうしたらいいか?
いつ・誰に・誰が・どのように根回しすればいいか?
を考えなければなりません。
③成果につなげる責任を果たす

これは言うまでもありませんね。
与えられた期限内に、任された目標をやりきるということです。

ありがとうございました。
何となくですが、全体像が理解できたような気がします。
昇進・昇格 管理職へのステップ:私の事例

前置きが長くなりましたが、ここからは「管理職へのステップ」として、私の事例を紹介したいと思います。
会社によって、管理職登用のプロセスは様々だと思いますので、そこはご承知おき下さい。
組合員から役職者へ

私の会社では、組合員から役職者(管理職クラス)になるときに試験があります。

組合員とは、労働組合の組合員のことですか?

その通りです。
会社によって、どのクラスまでが労働組合に加入しているのか様々だと思いますが、主任クラスまでは大半の会社が組合員扱いなのではないでしょうか?
役職者から管理職へ

役職者だからといって、管理職ではないのですか?

会社の方針や規模にもよるのでしょうが、主任クラスの全員を課長などの正管理職に昇格させることはできないと思います。ポジションも限られていますからね。
名刺交換した際に、相手の役職をよく見てみると、課長、副課長、担当課長、専門課長などと、課長にもいろいろあるなって思ったこと、ありませんか?

はいはい!
そうですね!〇〇課長ってありましたね!

ちなみに私の会社では、
主任クラスからいきなり課長になることは珍しく、
いったん、副課長、担当課長、専門課長などのステップを踏んで、
課長になるケースが多いですね。

昇進・昇格:私の昇進・昇格試験(管理職試験)

私の事例となりますが、
昇進・昇格試験について紹介したいと思います。
ただ、どの企業もそうだと思うのですが、
「ずっと同じスタイルの試験」ではないと思います。

どうしてですか?

受験者が「傾向と対策」をまとめていくからです(笑)
「過去問」と「模範解答」が蓄積されていくと、
本人の実力とは違う「運」の要素も左右されてきますからね。
もっとも、私はその「運」も重要だと思っていますが。

ご自身が昇進・昇格試験を受けたときには、どんな内容だったのですか?

一言で申しますと、「問題解決」試験でした。
ある状況が設定されていて、
これについて、あなたはどうしますか?
というのを回答するのです。

それを「問題解決」試験というのですか?

実を言うと、私は昇進・昇格試験に一度、落ちています。
そして、1年間かけて、この昇進・昇格試験の本質は何だろう?と自分なりに探求したのです
それで行き着いたのが「問題解決」だったということです。
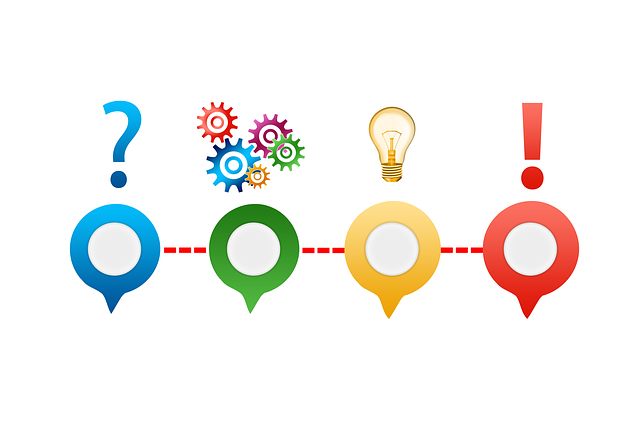

すみません、言っていることがよく分からないのですが・・・

し、失礼しました。つい、当時を思い出して、熱くなってしまいました。
ある状況が設定されていて、これについて、あなたはどうしますか? となった場合、「じゃ、こうします!」って回答したくなりませんか?

え!
それじゃいけないのですか?

いけないことはないのかもしれませんが・・・
私の行き着いた結論では、問題解決とは「あるべき姿と現状のギャップを埋める」ということだったのです。

「あるべき姿と現状のギャップを埋める」ですか?

その通りです。
先ほどの事例ですと、ある状況が設定されていて、これについて、あなたはどうしますか? という設問なのですが、私は以下のロジックで回答を作成しました。

す、スゴイですね・・・

実際、私の回答はかなりの高得点だったようです。
翌年、その評判を聞いた別の上司から、「お前の回答を提供してくれない?」と依頼がありました。聞くところによると、自分の部下に3年ほど試験に落ち続けている人がいるので、参考にしたいとのことでした。
私は自分の作成回答を丸ごと、その上司に渡しました(笑)

で、その方は合格できたのですか?

はい!
それもあって、私は自分の考え方が間違っていなかったことに確信を深めたのです。


なるほど
確かな実績に裏打ちされたものだったのですね。とても勉強になりました。

先ほども申しましたが、どの企業も「ずっと同じスタイルの試験」ではないと思います。
ですので、もしあなたの企業の昇格試験が問題解決試験でしたら、参考にしていただければ幸いです。
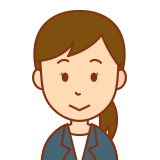
一度、不合格になったことにも意味があったようですね!
昇進・昇格 管理職に求められるビジネススキル
こちらでは、東証プライム上場企業の現役管理職として、様々なことに取り組んできた筆者(山ノ内公園)のビジネススキルを紹介させていただきます。
①聴く力について
ビジネスを行う上で、コミュニケーションスキルは必須です。
コミュニケーションスキルといっても、様々なスキルがありますが、相手のニーズを的確に捉えるためにも、聴く力は大事にしたいところです。
②書く力について
ビジネスを行う上では、報告書、提案書、企画書、プレゼン資料など、実に様々のドキュメントを作成します。
一般的にも言われていることですが、文章を書くうえで大事なことは、結論を先に書くことです。
PREP法など、いろんなテクニックがありますが、文章は一度、全体構成を仕上げてから、推敲した方がいいように思います。
最近の私は、メンバーが作った文章をチェックする立場になりましたが、「う~ん、ちょっと違うんだよね」と思うことが多いです。
文章は各自のクセのようなものがありますので、まずは自分のクセに気付き、一般的なテクニック(結論を先に書くなど)に従って、展開していくのがよいと思います。
③計画する力
どんなビジネスにおいても、スケジュールを立案するスキルは必要です。
簡単にいうと、何を、だれが、いつまでに、どうするのか?
人は弱い生き物ですから、ゴールが定まっていないと、つい「先延ばし」してしまいます。だからこそ、ゴール(締め切り)は重要です。
上司に割り振られた仕事ならば、そのゴール(締め切り、期限)を意識すればよいのですが、チームで取り組む仕事などはそんな簡単なことではありません。
いろいろな利害関係者が複雑に絡み合うからです。
だからこそ、日本人が得意?とする根回しも必要となってくるのです。
こういうと、「私には、根回しは向いていない」と思う方も多いかもしれませんが、根回しもコミュニケーションスキルの一つです。
計画する力に話を戻しますが、スケジュールに対してリスクも考慮し、具体的な数値計画や行動計画を落とし込むようにして具体化していきましょう。
④発想する力
最近、イノベーションという言葉をよく聞くようになりました。
先の読めない時代だからこそ、これまでの考え方に捉われず、自由に・柔軟に物事を考える力が必要なのですが、それを阻害するのは「偏見」です。
偏見とは文字通り、偏ったものの見方が原因なのですが、自由で柔軟な発想をするためには、この偏見を打ち破る必要があります。
本来、モノゴトには多様な側面があるのですが、人はとかく、ある一面からしかモノゴトを見れないようです(偉そうに言っている私も、よほど意識していないとダメです)
まずは、自身の偏見に気付き、そのうえで、視座・視野・視点を変えて、自由で柔軟な発想をしていく必要があるのです。
昇進・昇格 管理職に求められる意外なものとは?
ここまでは、昇進・昇格及び管理職に求められる「リアルな現実」を紹介してきましたが、忘れてはならないもっと大事な要素があります。
これは、管理職だけでなく、経営者にも求められる要素だと思います。
何だと思いますか?

えっと・・・すみません、教えて下さい。
それは「運」です。
運の悪い人は、何をやっても上手くいきません。
実際に、アメリカの企業などでは面接試験において「あなたは運がいいか」と問われることもあるそうです。

面と向かって、「私は運がいいです!」と答えるのは少々、恥ずかしい気もしますけど・・・
私も日本人なので、その気持ちは分かりますが、普段から「自分は運がいい」と思うように心がけていますので、いざ、そのような場面に出くわしたら、間違いなく「自分は運がいいです」と答えると思います。

山ノ内公園さんは、昇進・昇格試験のときに、何かしたのですか?
私は「出世の石段」で有名な「愛宕神社」を参拝しました。
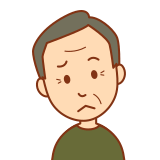
そこで、合格祈願をしたの?
合格祈願というより、日ごろの感謝の気持ちを伝えに行きました。感謝の気持ちこそが、自分の運を高めると思っているからです。
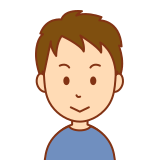
いわゆる、お守りや開運グッズについてどう思いますか?
個人の自由だと思いますが、お守りや開運グッズに「〇〇して下さい」とお願いするのではなく、感謝の気持ちを伝える方がいいような気がしています。
「〇〇して下さい」という思い(波動)は、「〇〇がない、〇〇に満たされていない」という思い(波動)と同じと言えるからです。
これは、引き寄せのテクニックとしても非常に重要な要素です。
スピリチュアル講座|波動の法則|目に見えないものにも波動はある

感謝の気持ちは自分も周囲も豊かにしてくれるものです。
仕事はできるけど、パワハラやセクハラをするような人の下では働きたくないですよね?
管理職を目指すあなたには、ビジネススキルだけでなく、人間的な豊かさも兼ね備えてほしいと思っています。
頑張ってください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
感謝いたします。
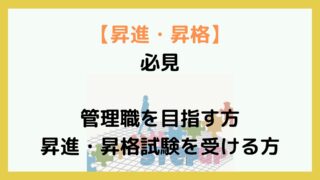
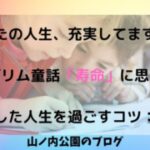

コメント